職場うつの多くはうつ病でなく「適応障害」、その違いとは
近年、メンタルヘルスの不調による休職や退職が増えている。15年以上の産業医経験があり、現在はビジネスパーソンの健康向上に関するサービスを手掛ける株式会社ベスリの吉田英司氏は、次のように話す。
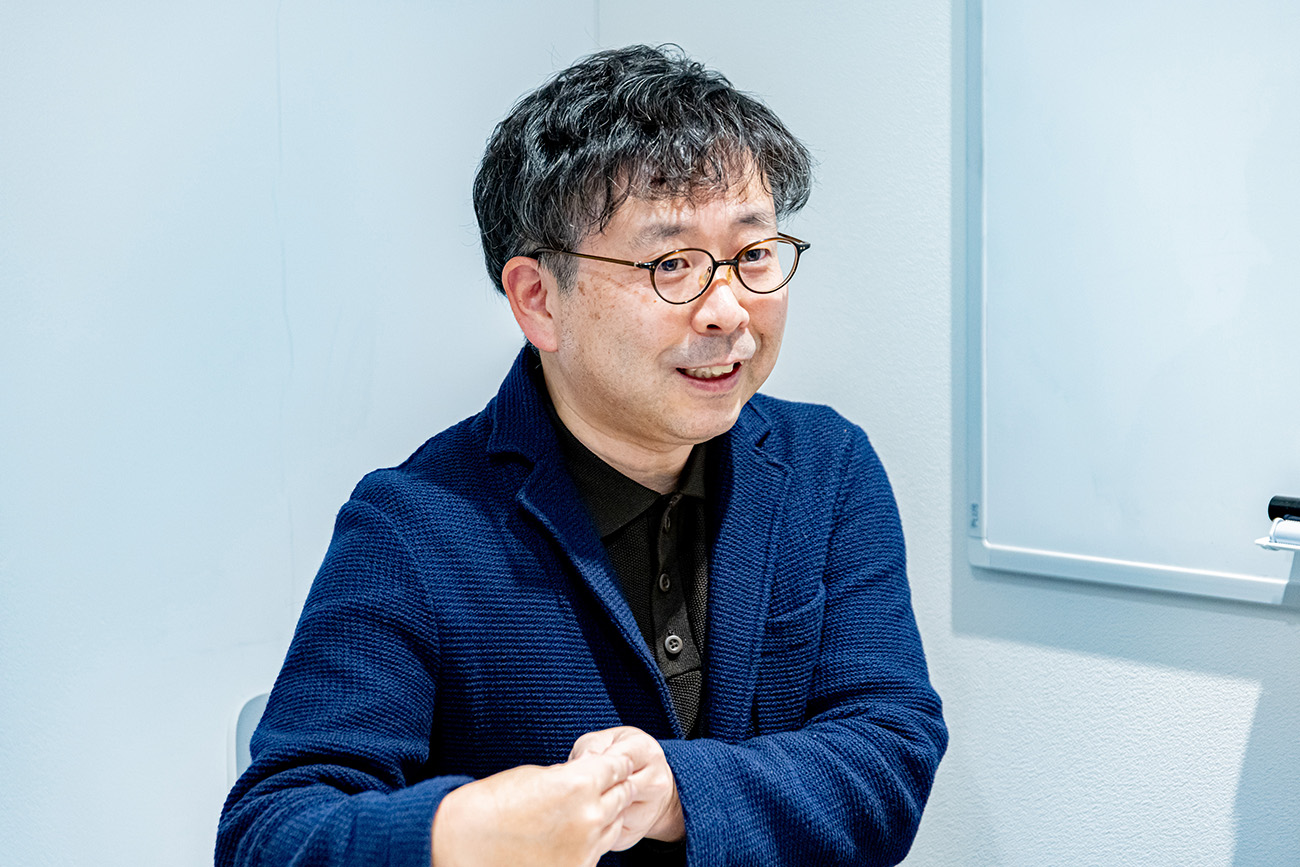
吉田 英司(よしだ えいじ)氏
株式会社ベスリ 代表取締役、産業医/心療内科医
臨床研修終了後、米系コンサルティングファームのベインアンドカンパニーでビジネスコンサルタントとして約3年間働く。会社組織の中で働くという視点から産業保健に興味を持ち、総合電機、半導体開発製造、外資IT、外資化学、大手通信グループなどの企業で、専属産業医や統括産業医として社員の健康をサポートしている。15年以上の産業医経験があり、これまでに500人以上の復職判定面談を行なっている。並行して、心療内科での外来診療も継続している。
「職場が原因のメンタルヘルス不調は、『職場のうつ』として20年ほど前から問題化していました。職場のうつのことを、多くの人は『うつ病』だと思っていますが、その8〜9割は『適応障害』に該当します。職場の人間関係や業務などの環境に対し、自分の性格や能力といった特性がうまく適応できないことによって発症するものです」(吉田氏)

吉田氏は、うつ病と適応障害の違いを、次のように説明した。
「単純化すると、うつ病は、どんな職場環境であっても憂鬱な症状が出てしまいます。たとえ良い上司や負荷の少ない業務といった環境でも、何かがきっかけで『上司が良い人で申し訳ない』『仕事がやりやすいなんて、何か悪いことが起こるのではないか』と思ってしまうのです。
一方の適応障害は、負荷の高い仕事や厳しい上司といった環境に、本人のキャパシティや感情が耐えられずに起こります。大きなプレッシャーのない、いわゆる“ふつうの環境”であれば憂鬱な症状は出ません。
つまり、メンタルヘルスの不調で休職している人の多くが、適応できる環境であれば活躍できる人材だといえます」(吉田氏)
コロナ禍によるリモート化も影響しているという。リモートワークによって精神的な負担が減った人も多い一方で、特に新入社員や転職者の負荷が高まる傾向にある。ストレスが減った人よりも増えた人が多いことで、メンタルヘルス不調による休職者は増加し続けているのだ。
せっかく復職した人が、再び休職してしまう理由
しかし実は、メンタルヘルスの不調でさらに難しいのは、体調が回復して職場に復帰しても、再発するケースが多いことだと吉田氏は指摘する。
「メンタルヘルスの不調で休職してその後復帰した人のうち、3年以内に症状が再発している人は半数近くにのぼります。これは無視できない数字です」(吉田氏)
もちろん、企業側が何も対策をしていないわけではない。リモートでも社内の交流を生み出す施策や、休職者に対して復帰後の配置換えやヒアリングといったフォローを行っているだろう。

それなのになぜ、復職したのに再発してしまうのか。理由の1つは、なぜ適応障害になったのかという原因の見極めが甘いままの復帰だという。
「適応障害で休職する人の中には、ハラスメントや労災レベルの環境で、誰の目から見ても『休職するのはしょうがない』というケースと、『ちょっと厳しいけどこのくらいならあるよね』という環境でも体調が悪くなってしまうケースがあります。後者の場合、復職の際に配置換えをして前の厳しい上司はいなくなったのに、また別の上司とのやり取りでストレスを感じてしまい、適応障害が再発してしまうことがあるのです」(吉田氏)
世の中、相性の悪い人は0にはならない。上司でなく、取引先で厳しい人と出会う場合もあるだろう。休職者が復職する際には、会社が上司や業務量といった環境をなるべく改善することが望ましいが、本人のストレス耐性を高めることも、長く活躍してもらうには重要な視点なのだという。
また、本来は復帰すべきではないタイミングで焦って復帰してしまうケースも、症状が再発しがちだ。たとえば、「まだ仕事ができるかはわからないが、金銭的に心配になってきた」と、適応障害が治っていないのに、本人が希望して復職する場合などが該当する。

「適応障害になった人が通う心療内科・メンタルクリニックの医師は、患者が復帰の意思を見せれば『復職してよい』と診断書を出します。これは難しい事情なのですが、お金がない状態もストレスの1つになるわけです。患者はストレスが原因で通院していますから、そのストレスを解消するためにも復職したほうがよいと判断する。しかし、適応障害は治っていないため、復帰してもすぐ再発してしまい、再度休職してしまうのです」(吉田氏)
心療内科の外来では、1人あたりにかけられる時間は非常に短い。カウンセリングなどで1人ひとりとコミュニケーションをとるクリニックもあるが、それでも1人20分〜30分、頻度も数週間に1回が限界だ。
「今の医療機関では、体調不良の原因を聞くことはできても、それに対してどのように対応するかをいっしょに考えるのは難しいのが現状です」(吉田氏)
では、休職者に復職してもらい、かつ再発を防ぐにはどうすればよいのだろうか。
業務遂行性が高い状態で復職できる「リワーク」とは
吉田氏は「まず体調を治すのが最優先」としたうえで、特に適応障害では「復帰した後に、組織の中でどう働くか」を考えることが重要だとする。
そこで注目なのが、復職準備ができる「リワーク」だ。「return to work」の略語で、職場復帰に向けたリハビリテーションプログラムのこと。休職者が働いている時とほぼ同じ生活をし、実際に施設まで通所して復職に向けた支援を受けることで、業務遂行性が高い状態での復職が可能となる。
「適応障害はまだ治療法が世の中に浸透していないのが現状です。しっかりと治療できれば、もっと早く回復して活躍できる人は多いはず。リワークの認知度が高まってほしいと考えています」(吉田氏)
リワークには「医療」「福祉」「地方自治体」の3つの実施機関がある。利用方法や費用に差はあるものの、プログラム内容や会社との連携の有無は施設ごとに異なるため、導入を検討する際には施設を見学するのもおすすめだという。

自信を持って復職できるように!そのプログラム内容とは
プログラムは集団講義が多く、認知行動療法やマインドフルネス、ストレス耐性に関するものやコミュニケーションなど多岐にわたる。これに加えて、ベスリのリワークで特徴的なのは、「再発防止策」の作成と発表だ。
「たとえば、ベスリのリワークでは、20〜30ページほどのパワーポイント資料を作成します。そして、同様にリワークに通う人や講師の前で、『なぜ、自分がこのような体調になったのか』『どうすれば再発を防止できそうか』といった発表を行います」(吉田氏)

発表後には周囲からフィードバックを受ける。このフィードバックが大きなポイントなのだという。なぜか。
「ふだん、職場では自分の考えや行動に対して、面と向かって意見されることはなかなかありません。もし機嫌が悪そうにしていても、わざわざ同僚は指摘しませんよね。それに、万が一何かいわれると腹立たしかったり、うとましかったりするものです。
一方、リワークには自分と同じような状況の人が通っていますから、指摘されたときに素直に受け入れやすい。周囲だけでなく、自分の行動や考え方もメンタルヘルスの不調につながっていた可能性に気付けることで、復帰した後の参考になりやすいのです」(吉田氏)
こうしたポイントから、プログラムを受けて復帰した従業員がいる企業からは、「こんなに元気になるのか」「どうやって休職時の状況から変化させたのか」と驚きの声がよく上がるのだという。
「これまで、メンタルヘルスの不調では『なんとなく、症状が出なくなってきたから復帰できるかも』と職場に戻るケースも多かったのではないでしょうか。反対にベスリのプログラムは、グループディスカッションやフィードバックを通して不調の原因をしっかり分析します。それによって、根拠や自信を持って復職できるのです」(吉田氏)
実際、リワークの効果はデータでも確認できる。吉田氏によると、リワーク経由で復帰し、半年後も休職せずに働き続けている人は9割程度。ベスリのリワークにいたっては100%だという。
人事が知るべき、リワークに通ってもらうためのポイント
もちろん、リワークも魔法の杖ではない。吉田氏は人事へのアドバイスとして次のように話す。
「休職した人は、まず睡眠障害などで日常生活が満足に送れない状態がほとんどです。そこから日常生活が徐々に送れるようになり、社会生活にも復帰し、職場に復帰する——と段階を踏みます。ある程度の日常生活が送れるようになったら、比較的早期にリワークの提案をするのがおすすめです。というのも、本人が体力的にほぼ万全の体調になってからリワークの話をしても『これからさらに数ヵ月をかけてリハビリをするのか』と感じてしまい、なかなか行く気になりません」(吉田氏)
一般的にリワークに通う期間は3〜6ヵ月、ベスリのリワークでも2ヵ月間のプログラムに加え、産業医面談などで3.5ヵ月はかかる。「元気になったから働きたい」と思う本人にとって、さらに数ヵ月も復職が伸びるのはもどかしいだろう。休職から1ヵ月後くらいに、復職ステップとしてリワークを案内するのが、前向きに通ってもらうポイントだ。
また、「ルール化」もおすすめ。休職者によってリワークに行く人/行かない人がいると「なぜ、自分だけ?」と感じてしまう人もいることから、「半年以上休職した人」「休職が2回目以上の人」といった形でルール化すると、納得感を持って通ってもらいやすいという。
その他、リワーク施設側との連携も重要になる。
「繰り返しになりますが、適応障害は、環境と個人の適応がうまくいかないことによって発症します。リワーク施設が本人の話だけ聞いてしまうと、偏った情報でリハビリをしてしまい、本来の原因に対する解決策を考えられずに復帰してしまうことにつながります。正しい解決策を考えるためにも、企業から休職者に関する情報を共有してもらえるとありがたいです」(吉田氏)

休職者の対応に先手を打って、自信を持って復職してもらおう
現状、メンタルヘルス不調からの復職に関して、再発防止の観点から徹底的に取り組む企業はまだ少ない。企業ごとの対応もまちまちで、大企業では産業医面談を頻繁に実施していることもあるが、余力のない企業では診断書だけで従業員の状況を把握しているケースも多い。
「診断書だけで判断すると、どうしても休職者への対応が後手に回りがちです。復帰した後も職場に適応できそうかしっかりと考えるためには、休職者と定期的にやり取りをして、体調を確認するとよいでしょう。また、リワークに通っているとはいえ受け身にならず、能動的に復帰までのステップを示すことが人事部門の役割です」(吉田氏)
増加傾向にある休職者に対して、いかに自信を持って復帰してもらえるか。人手不足の昨今は、外部からの採用だけでなく、既存人材へのマネジメントも非常に重要といえる。企業だけでなく本人の幸せにもつながる手段の1つとして、リワークは今後広がっていきそうだ。
再休職を減らすリワークについて知りたい方へ
産業医と総務人事がつくった、再発防止に本当に必要なリワークに興味を持たれた方は、詳細や復職体験記が読める「ベスリのリワーク」 をご覧ください。




































