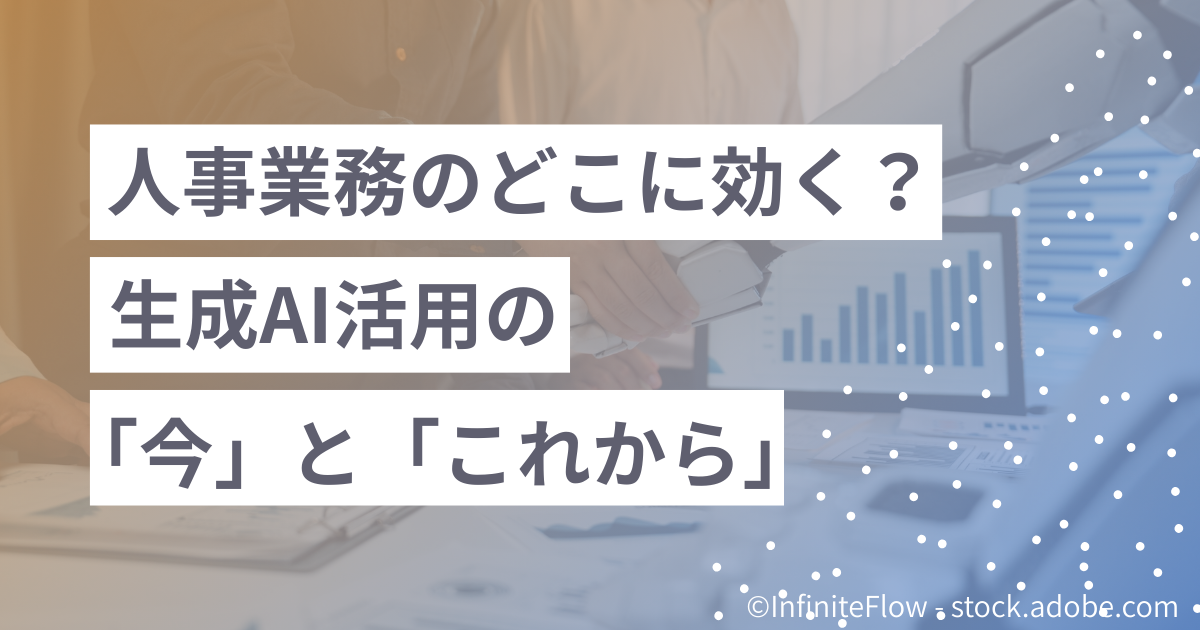前編「「人事領域の生成AI活用」を日米比較で読み解く——“質の高い”利活用を阻害している日本特有の文化とは」もあわせてお読みください。(本稿だけでもお読みいただけます)
データ基盤を整備する重要性——生成AI活用を阻む「データのサイロ化」とは
前編からの繰り返しになりますが、生成AIは、単なる業務効率化のツールでなく、人事戦略を推進する強力な土台となる可能性を秘めています。そのために、「役割とスキルの可視化」と「データ基盤の整備」の観点が重要なのです。
役割とスキルを可視化することで、社内の各ポジションや役割で「どのような業務が行われ」「どのようなスキルが求められているのか」が整理でき、データとして蓄積できます。
これにより、従来は個人の経験や勘、あるいは暗黙知に頼りがちだった「スキル」という曖昧な概念を、AIが客観的に扱えるデータに変換できます。この土台があって初めて、生成AIは候補者や従業員のスキルデータと照らし合わせ、精度の高いスキルマッチングやキャリア提案を行えるようになるのです。
これは、採用・配置・育成の高度化につながるだけでなく、従業員自身がキャリアの方向性を主体的に描きやすくなる効果も期待できます。
そして、もう1つの柱「データ基盤の整備」は、採用、人事管理、勤怠、研修といった各システムに分散して存在するデータを横断的に統合することです。
多くの企業では、こうしたデータがシステムごとに閉じて管理されている“サイロ化”の状態にあり、情報が連携されず、全体を俯瞰した活用が困難になっています。
統合的なデータ基盤の“その先”、AIエージェント同士が協業する可能性
データの分断を解消するためには、API連携などを通じてシステム間のデータを結びつけるとともに、「データレイク[1]」のような仕組みを活用し、さまざまな形式のデータを一元的に蓄積・管理できる環境を整えることが重要です。
注
[1]: 人事に関連する構造化データ(数値データ)と非構造化データ(
データには、勤怠記録や評価スコアのように項目が明確に整理された構造化データだけでなく、履歴書のPDFや自己申告コメント、面談メモといった形式が定まっていない非構造化データも含まれます。データレイクは、こうした多様なデータをそのままの形で蓄積できるため、AIによる横断的な分析や洞察を可能にします。
統合的なデータ基盤を持つことで、生成AIは人事ライフサイクル全体を俯瞰し、個別の業務を超えた最適化や、将来を見据えた戦略的提案が可能になります。
さらに一歩進んで、これからのAIデータ基盤は、単にデータを一元化するだけでなく、自社しか持ち得ないデータやノウハウを学習したAIエージェント同士が自律的に連携し合う「エコシステム」へと進化させる視点が不可欠です。
その中核技術となるのが、AIエージェント同士が対話し、協業するための共通言語となる仕組み(プロトコル)です。そして、この自社独自のAI基盤には、豊富な外部接続用の窓口(エージェント)を用意しておくことがきわめて重要になります。
これにより、たとえば「自社の評価制度とキャリアパスに精通したAIエージェント」が、「外部の最新の労働市場データを持つ他社のAIエージェント」とシームレスに連携し、従業員1人ひとりに対して、社内外の選択肢を含めた最適なキャリアプランを提案するといった、より高度な活用が可能になります。複合的で戦略的な人事施策は、一社単独で保持しているデータだけでは成し得ません。開かれたAI基盤の設計が今後の鍵を握るでしょう。