成果を出した「B面情報」発信の事例
徳力氏が手本としてまず紹介したのは、NECグループのSIer企業であるNECネッツエスアイの取り組みだ。同社は、自社の特徴が採用市場で伝わりづらいという課題を抱えていた。
「多くのSIerは自社製品を持たないため、SIer各社の採用パンフレットの社名を隠すとどこも似たように見えてしまいます。そのため、企業文化の違いが伝わりにくい。その結果、学生や求職者から選んでもらいにくい状況でした」(徳力氏)
この状況を打開すべく、同社は社員の声を中心とした「B面情報」の発信を開始。たとえば、「kintoneでアプリを作り、課題解決をどんどん進めているウワサの調達本部を取材してみた!」と題した記事では、ふだんは表に出ない部署の実務や社員の様子を紹介した。こうした試みにより、採用エントリー数が1.6倍に増加し、社内の風通しの良さを示すスコアにもポジティブな変化があったという。
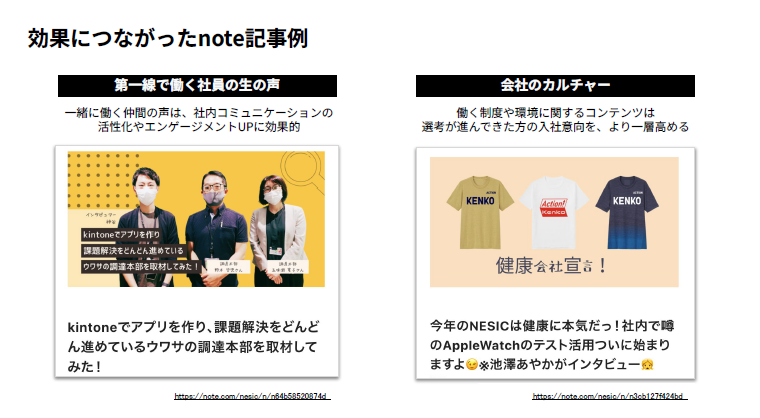
また、マーケティング領域で知名度のあるベーシックも、自社の認知度不足に悩んでいた。サービスは知られているものの、企業そのものへの理解が進んでおらず、採用活動に苦戦していたのだ。
そんな同社も、「「疲弊しない営業」の組織づくりを目指していたら、ferret Oneのインサイドセールスに行き着いた話」のような「B面情報」の発信に活路を見いだし、先輩社員の入社の決め手や志望動機、会社のカルチャーを記事で積極的に紹介。結果として採用サイトからの直接応募は約3倍に増加し、内定承諾率も90%に達した。
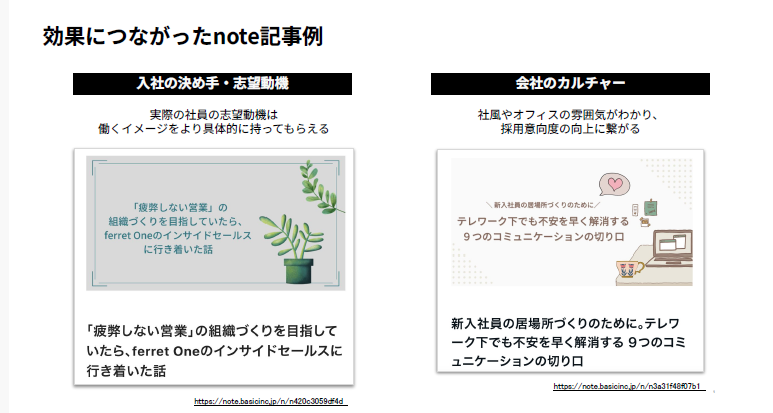
「両社の共通点は、バズを狙う記事ではなく、求職者が知りたい情報をネット上に継続的にストックしていった点にあります。知りたい人がいつでもアクセスできる環境を整えること。これが企業を選択肢の1つとして意識してもらうきっかけになります」(徳力氏)
内定承諾率を高める情報設計に成功した事例
次に紹介した事例は、GMOインターネット。同社は、内定承諾率の向上に向けて「面接前に読んでほしい情報」を記事にまとめ、あらかじめ候補者に提示する取り組みを行っている。
その1つが、「育休を取得したパパ2人が語る!家族との時間を大切にする働き方とは?」という対談記事だ。制度の概要だけでなく、育休を実際に取得した社員が語るリアルな経験談や、復帰後のキャリアについても紹介されている。
「育休制度は、本当に取れるのか? 復帰後のキャリアはどうなるのか? といった不安が大きいものです。こうした懸念に真正面から答える記事は、求職者にとって後押しになりますね」(徳力氏)
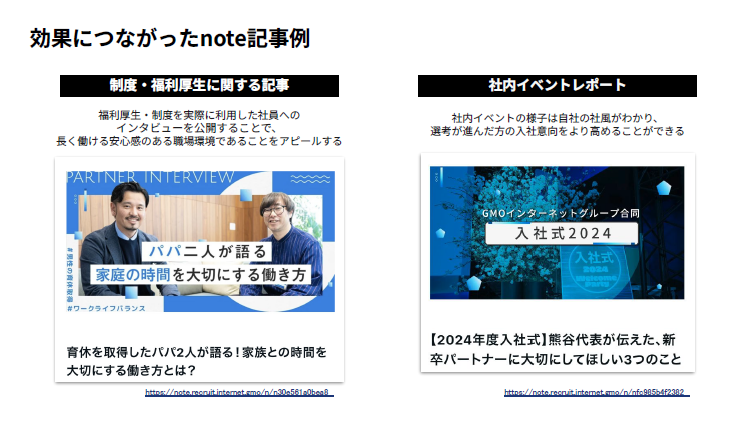
さらに特徴的なのは、社員の本音が見える点だ。
「記事に課題や悩みなどの本音が混じっていることで、かえって信ぴょう性が増すんです。きれいな情報だけでは『本当かな?』と疑われてしまいますから。等身大の情報にこそ、信頼感が宿るのではないでしょうか」(徳力氏)
こうした施策の結果、GMOインターネットの採用関連記事は内定承諾者の100%が認知。さらに、面接前の前段階で企業理解が深まることで、面接時間をより有意義に活用できるようになったという。
これら3社の事例が示しているのは、採用ブランディング=派手なプロモーションではないということだ。求職者が本当に知りたい情報を、丁寧に、着実に積み上げていく。その地道な取り組みこそが「この会社で働いてみたい」と思われる理由になる。企業の内側にあるリアルな日常を少しずつ外に開いていくこと。それこそが、今の時代に求められる採用力強化の手法といえるだろう。























