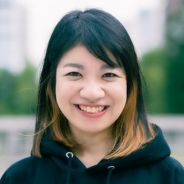会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- 対談《ウェルビーイング》連載記事一覧
-
- スタートアップの「ウェルビーイング経営」の舞台裏——事業成長につながる採用・制度・カルチャ...
- 「ウェルビーイング経営のリアル」を専門家×実践者が語る! “働く幸せ”を追求する成功企業の...
- この記事の著者
-
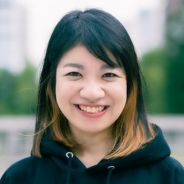
中釜 由起子(ナカガマ ユキコ)
中央大学法学部卒。朝日新聞社で記者・編集、新規事業担当、Webメディア「telling,」創刊編集長などを経て、2019年に株式会社ジーニーへ。マーケティング、全社広報・ブランディング統括などに従事。2023年4月にテックタッチにHead of PRとして入社。2023年10月より、Head of Marketin...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
-

齋藤 大輔(サイトウ ダイスケ)
写真家。1982年東京生まれ。
東京造形大学卒業後、新聞社などでのアシスタントを経て2009年よりフリーランス。コマーシャルフォトグラファーとしての仕事のかたわら、都市を主題とした写真作品の制作を続けている。
主な写真展
「sight seeing #1,#2,#3,#4,#5」2007年~200...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です