これからの人材戦略では「時間」の使い方が問われる
髙浪司氏(以下、髙浪) 今度の労働基準法(以下、労基法)改正では、労働時間の情報開示義務化も大きなテーマの1つです。情報開示は「長時間労働の是正のための監視」だけではもったいなく、採用・定着・投資家対話で勝つための「見える化」にしていきたいと考えています。たとえば平均残業、45時間超の割合、勤務間休息の確保率を部門別にダッシュボード化するなどで、打ち手(人員計画や業務再設計)が早くなる可能性があります。
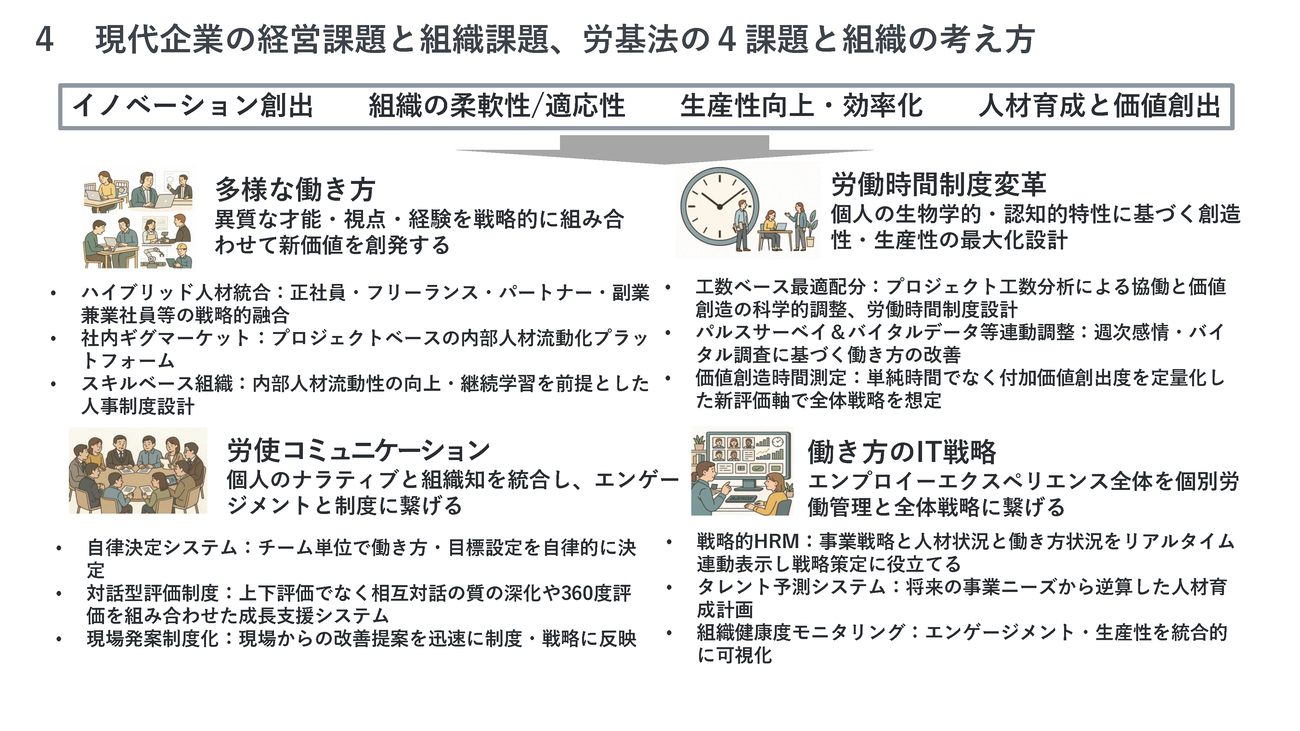
[画像クリックで拡大表示]
松井勇策氏(以下、松井) そうですね。ただ私は、それにとどまらず、「働き方の質」を見直し、ウェルビーイングを含めた環境づくりへと向かう流れだと捉えています。だからこそ、これからの人材戦略では、「時間」をいかに使うかが問われてくるのだと思います。
髙浪 ええ。そのために勤怠管理システム化はもはや当然の前提であり、テクノロジーの活用は不可欠です。現場に制度を根付かせるには「やることを減らす」と「学ぶ時間を確保する」の両輪の必要性を感じますが、そこにはジレンマが存在していると感じています。
今は「残業を部下に割り振ることができない → 最後は管理職が巻き取る」に陥りやすい。本当は時間外でも横につき、やって見せるOJTで鍛えたいのですが、上限や運用の制約でそれが難しく、結果として「自分でやったほうが早い」に流れてしまう。さらに、やる気のある部下にストレッチな仕事を渡したいのに、稼働上限や平準化の圧力で任せ切れない——この2重の苦悩が現場にあります。

髙浪 司(たかなみ つかさ)氏
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ピープル・コンサルティング アソシエートパートナー
外資系コンサルティングファームにて、会計領域のコンサルティングや、組織再編・事業統合に伴う事業モデル設計に従事し、大規模な業務改革・構想策定を得意とする。現職のEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社では、人事戦略を起点としたグローバル・ビジネス・サービスの変革を推進。業務の高度化・効率化を通じて、デジタルシフトに伴うワークフォース変容に対応し、次世代型の人事機能・人事オペレーティングモデルの構築や、スキルベースアプローチの導入によるタレントマネジメントの進化に注力している。
松井 そこは本当に大きな論点ですね。私も基本的には「量が質を生む」側面はあると考えています。もちろん、法制度は権力の非対称性に対する“保護”の機能を持つべきですが、それだけが強調されすぎると、本来の目的からズレてしまう懸念もあります。
今後は、中長期的な視点で、たとえば時間外労働の上限規制の見直しや、ホワイトカラーエグゼンプションの再検討、管理監督者の定義の柔軟化など、現場の実態や職種に即した制度改革も必要になってくると思います。
たとえば私が関与している企業に、育児期の女性が8割という体制ながら、生産性と価値向上を実現しているBPO事業会社があります。その企業では、業務を完全に細分化して見える化したうえで複数管理職制を取り、社内コミュニティでナレッジシェアを行っています。
また、週の労働時間を1時間から40時間までいつでも変更できる体制を取り、完全フレックスとテレワークで飛躍的に発展しているスタートアップ企業もあります。このような、よく考えられた労働時間制度や労務管理が全体として、企業文化や事業価値につながってこそ意味があると思います。単独の制度のみをただ設定するだけではあまり意味がないのではないでしょうか。
髙浪 まさにそうだと思います。しかしながら、制度をどれだけ整えても、それが実際に価値につながっているのかは、見えにくいのが現実です。
かつては「RPA(ロボティックプロセスオートメーション)で〇〇時間削減した」といった効率化の話が中心でしたし、最近ではAIの活用も進んでいます。働き方改革や業務効率化で時間を削減したとして、「その時間を何に再投資したのか」が問われています。削減した時間が単に「業務量をそのまま減らす」だけで終わってしまえば、労働時間の短縮と引き換えに、成長の機会や挑戦の場を減らしてしまうリスクもあります。本来なら、浮いた時間を自己学習、チーム改善、顧客接点、新たな価値創出のいずれにどのように再配分したのか、それによって従業員や組織にどんな変化が起きたのかまで語れるようにすべきです。
しかし実際には、それによって生まれた時間が従業員の成長やウェルビーイングにどうつながったかを示す有価証券報告書や統合報告書の事例は少ないように思えます。
松井 結局、それは「人的資本をどう使っているのか」という問いに行き着くんですよね。

松井 勇策(まつい ゆうさく)氏
産学連携シンクタンク iU組織研究機構 代表理事・社労士
雇用系の産学連携シンクタンクの代表理事・社労士。先進的な雇用環境 整備について、特に雇用系の国内法や政策への知見を軸に、人的資本経営の推進・AIやIT・ブランディング関係の知見を融合した支援を最も得意とする。株式会社リクルート出身、同社の東証一部上場時には事業部サイドの監査や整備を推進。退職後に社労士・組織コンサルタントとして独立、のち情報経営イノベーション専門職大学(iU)に客員教授として招へい(専門:人的資本経営・雇用政策)、2024年産学連携シンクタンク設立。
髙浪 はい。だからこそ、「削減された時間を何に使ったのか」「そこからどんな成果が生まれたのか」を見える化する必要がある。もちろん、多くの企業が従業員からフィードバックを得る努力はしているものの、サーベイで本音が語られているのか、どう評価するかという点は、非常に悩ましい問題です。
松井 エンゲージメントサーベイは確かに有効な手段ですが、それをどう解釈し、どう活かすかは、最終的に企業側の意志に依存します。
今度の労基法改正は、「働き方の質」に目を向ける絶好のきっかけになります。「時間を何に使うのか」「その使い方でどんな価値を生むのか」を、人的資本の投資や制度設計に落とし込んでいく。それくらい踏み込んで初めて、人に投資する意味が現場に届くようになると思いますね。そうした見えにくい価値を捉えるために、いま企業に求められているのが、蓄積されたデータをどう活用するかという視点です。























