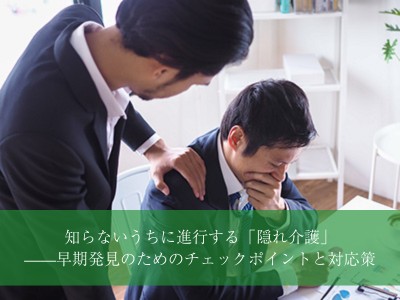「評価・環境・制度」記事一覧
-
制度設計と魅力的な制度広報の手法—制度は“ルール”ではなく“メッセージ”である—
採用活動において、企業はつい「制度」を内部向けの仕組みや、他社と比較するための“条件”として扱いがちです。しかし、実は制度こそが企業の価値観を...
 1
1 -
「労基法大改正」で労務管理と経営戦略が接続 その対応になぜ「TeamSpirit」が最適なのか?
2027年に予定されている労働基準法(以下、労基法)の大改正。その根幹にあるのは、人々の“働き方を自由にすること”であり、これまでの人的資本経...
 60
60 -
「組織文化」の人気記事をチェック——ラクスやオルビスの成長を支える戦略的なカルチャー浸透施策など
HRzineで掲載してきた数々の記事を、注目のテーマで振り返る「ワンテーマプレイバック」。今回は、組織の一体感を高め、企業の成長に大きな貢献が...
 0
0 -
労働基準法大改正 対談【後編】——重要なのはツールにすぎない法令・政策を経営や人事施策につなげること
ルールとして眺めているだけでは、2027年予定の労働基準法改正の本質は見えてこない。問い直すべきは、働き方そのものの前提であり、それを支える制...
 2
2 -
労働基準法大改正 対談【前編】——働き方改革を超える人事戦略の転換点、まず働き方の個別化へ舵を切れ
いま、働き方の前提が大きく変わろうとしている。2027年以降に予定される労働基準法の大改正は、単なるルール変更にとどまらない。分散型組織や副業...
 3
3 -
セゾンテクノロジーの健康経営は経営のためではない 社員の豊かな人生を願う社長のライフワーク
社員の健康は企業経営における重要課題の1つである。株式会社セゾンテクノロジーでも、代表取締役の葉山誠氏が旗振り役となって、社員の健康向上にまつ...
 0
0 -
「日本型スキルベース」へ移行せよ —まず行うべきこと&日本人特有の「恥ずかしさ」とどう向き合うか
スキルベース組織とは、スキルを中心とした人事マネジメント手法の1つであり、欧米のリーディングカンパニーが導入を始めたことで注目されている。本連...
 4
4 -
ユーザベースは成果にシビアだから働きやすい⁈ CHROに聞く「自由と責任」を追求する組織の在り方
「働きやすい職場づくりと個人の高パフォーマンスの両立を諦めずに追求している企業」にフォーカスを当て、どのように制度や風土を整えているのか、また...
 0
0 -
「“隔”週休3日制」にたどり着いたKAKEAI 週休3日制の課題をどう捉え、改善し、生産性向上を実現したのか
働き方の多様化が進むいま、「週休3日制」は1つの選択肢として注目されている。しかし企業にとっては導入のハードルが高いのも事実だ。そんな中、完全...
 16
16 -
知らないうちに進行する「隠れ介護」——早期発見のためのチェックポイントと対応策
日本は超高齢社会に突入し、「隠れ介護」という新たな社会問題が注目されています。隠れ介護とは、家族の介護を担いながらも職場や周囲にその事実を伝え...
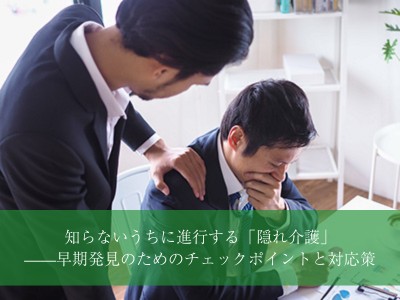 0
0 -
AOKIに聞く オフィスカジュアルが広まる中で従業員の服装をどう規定し、どう自由化すればよい?
働き方の多様化やハイブリッドワークが進んできた今日、スーツから離れ、オフィスカジュアルが広まるなど、働く場面での服装はかなり変化してきている。...
 2
2 -
「制度以上に風土が大事」 育休取得の男女別傾向と、復帰後の離職を防ぐヒントをXTalentに聞く
共働きで働く世代が増える中、男性の育休取得率が人的資本開示の重要指標の1つとなるなど、男女かかわらず育休取得の機運が高まっている。一方で、XT...
 1
1 -
Z世代に対応する職場づくりが企業を進化させる そのとき人事と経営層が果たすべき役割とは
現在の経営層の中心であるX世代(1965年~1980年に生まれた世代)と、若手のZ世代(1997年~2012年に生まれた世代)との間には大きな...
 0
0 -
なぜ三井住友海上は「育児と仕事の両立支援サポートブック」を作成しマネージャー1200名に配布したのか
子育てで急な休み・早退をする同僚に対し、SNSなどでは「子持ち様」と揶揄する声が上がる現在。メンバーに対し、マネージャーはどう接するべきなのか...
 3
3 -
ギフトでエンゲージメントを向上! 福利厚生にも対応したギフティの従業員向けソリューションとは
人は感情で動くものである。会社で働く人たちは合理性だけで活躍するのではない。「会社は自分たちのことを大切に思っている」と感じられることも重要だ...
 2
2 -
働きがいのない「ゆるブラック」企業はなぜ生まれた? 若手を“鍛える”企業に共通する「4つの環境」とは
終身雇用制度が終わりを迎え、キャリア自律の重要性が増す日本では、若手社員(以下、若手)を取り巻く環境が大きく変化している。たとえ有給が取りやす...
 0
0 -
両利きの組織を成功させるための組織制度設計とは——パーパス経営、評価設定および“組織開発”
現代を生き抜く企業において不可欠ともいえる「両利き」の経営。それを実現するために必要な組織制度設計とは? 今回ではVUCAへの理解と、人材・組...
 1
1 -
育休や時短などの制度だけでは「働きづらい」共働き世代 転職理由から見える“新しい価値観”とは
夫婦で仕事をしていても家事や育児などは女性の役割とされていた過去と比べ、現在の共働き世代は、「家事も育児も夫婦でフェアに分担したい」という価...
 7
7 -
「はたらく人」の本音がわかる! 人事も気になるパーソルキャリア「はたらクイズ」8つの回答
世の中には、慣例的に行われているはたらき方や、改めて考えてみると疑問が生まれる「はたらく」にまつわる事柄が数多くあります。パーソルキャリアでは...
 0
0 -
海外赴任者の子育てをどう支援する? 多様化する赴任者への医療費、子育てサポート、為替・物価対策を解説
多くの企業にとって海外赴任者は、海外戦略を考えるうえで欠かせない重要な存在です。一方で、赴任者へのサポート体制にはさまざまな課題が存在します。...
 0
0
Special Contents
AD
76件中1~20件を表示